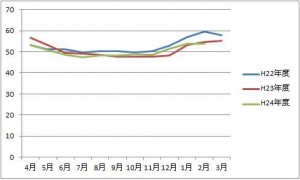中央畜産会は6日、東京都内で地域再生フォーラムを開いた。これは東日本大震災をはじめ、これまで全国各地で蒙った自然災害や原発事故により畜産が直面した課題等を整理し、今後の畜産において復興・再生のプロセスの参考にするもの。3つの基調講演と8つの報告が発表された。
東北大学の中井裕教授は、東日本大震災における畜産の被害状況を整理し、飼料工場の配送体系や乳業界での危機管理体制の取り組み、地域レベルでの停電時の電源確保対策などを紹介し、「地域再生に持続可能な畜産事業を構築することが必要で、地域内連携、耕畜連携、農協や畜産関連ネットワークとつながることが大切」とした。
福島県の酪農家、三瓶恵子さんは「T・から始める酪農」と題し、原発事故によって避難し、農場を移転せざるを得なくなった経緯と現在の状況を話した。同氏夫妻は移転に当たり弟夫婦と共同で株式会社「T・ユニオンデーリイ」を設立、被災から3年目に入る今、「常に前に向かっていくことを大切にしたい」と述べた。同牧場の「T」は以前の住所、自分や弟夫婦の名前の頭文字とのこと。
日本獣医生命科学大学の小澤壮行教授は、過去の自然災害等から復興した事例の特徴として「地域・後継者・従業員・同業者等が一体となった展開、“モノからヒトへのシフト”を強調したい」と述べた。さらに、復興関係資金の助成事業・制度資金の有効利用における行政の力、法人化・共同化による負担軽減とスケールメリットの発揮の3点をあげた。さらに普段からのライフライン整備、正しい情報取得と発信が大事とした。
雲仙普賢岳の噴火により被災した長崎県・雲仙生乳生産組合の高原和光氏は、共同で農用地を集積し、酪農を再開したプロセスを報告した。同氏は、補助事業等の利用で牛舎・施設・採草地を整備し、被災前には経産牛75頭だったが、現在は同100頭、育成牛50頭と、和牛・乳雄・F1肥育230頭へと経営を拡大している。再建に当たっては積極的な姿勢が大事、と述べた。
また、中越地震からの畜産の復興、口蹄疫による被災からの復興、鳥インフルエンザからの復興、風評被害への対応などが話された。(文責:関東支局)