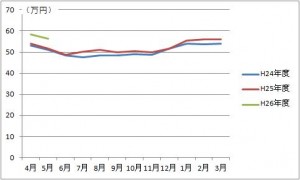産業動物専門学術スタッフ(獣医師)募集:共立製薬(株)
2014 年 6 月 6 日
共立製薬(株)では、産業動物専門学術スタッフ(獣医師)を募集している。
同社は、1955年動物用医薬品専門企業として誕生。「人と動物と環境の共生をになう」の企業理念のもと、日本の動物医療のリーディングカンパニーとして活躍している。詳細は下記のとおり。
求人数:関東エリア(1名)、九州エリア(1名)
業務内容:弊社産業動物担当MRのテクニカルサポート
資格:獣医師
※養豚場に勤務経験のある獣医師はとくに優遇いたします。
勤務先:PA関東営業所:さいたま市大宮区大門町3-105 やすなビル
PA鹿児島営業所:鹿児島市中央町18番地1 南国センタービル3階
※給与、賞与その他は弊社規定に準じます。詳細はお電話ください。
連絡先:共立製薬(株)PA営業本部 TEL:03-3264-7559 (担当:桜井)
なお、同社PA熊本営業所は下記の通り移転することになり、移転に伴い、営業所名もPA鹿児島営業所に変更となる。
新) 共立製薬(株) PA鹿児島営業所
〒890-0053 鹿児島市中央町18番地1 南国センタービル3階
TEL:099-296-8661 FAX:099-251-3210
旧) 共立製薬(株) PA熊本営業所
〒861-8011 熊本市東区鹿帰瀬町463-18
TEL:096-292-7211 FAX:096-292-7213
業務開始日: 平成26年6月16日より
お問い合わせ先 03-3264-7559(共立製薬(株) PA営業本部)
TrackBack URL :
Comments (0)