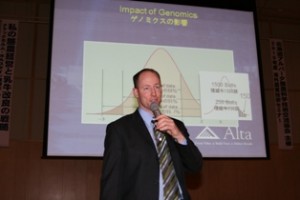「繁殖性」「長寿性」を改善しないと収益を上げることはむずかしい
2011 年 2 月 23 日
北海道アルバータ酪農科学技術交流協会は23日、酪農学園大学で海外農業技術セミナーを開催した。
講師は、カナダ・ケベック州にあるクラックホルム・ホルスタイン牧場主のデイビッド・クラック氏。
同氏は優秀なブリーダーとして知られ、またアルタ・ケベック州マネージャーとしても活躍している。
同氏は、乳牛の遺伝改良の方向性、アルタ社の種雄牛の紹介、同牧場の優良雌牛の紹介という3部構成で講演した。
乳牛の遺伝改良の方向性では、乳量や体型(乳房、肢蹄など)はめざましく改良されたが、繁殖性、牛群滞在期間は低下しており、「この二つを改善しないかぎり収益を上げることはむずかしい」と指摘。
そのためには、自分の農場に合った遺伝プログラムと目標を定め、従来の生産能力形質、機能的体型形質に加え、健康+生存形質を重視すべきであるとして、DPR(娘牛の妊娠率)、HL(牛群寿命)、PL(生産寿命)、MCE(分娩難易度)などの遺伝評価の活用について解説した。
詳報はDairy Japan 4月号で。
TrackBack URL :
Comments (0)