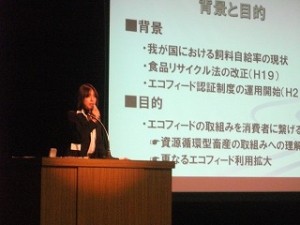12月19日(月)、東京都内で、「平成23年度飼料イネの研究と普及に関する情報交換会」を開かれた(共催:畜産草地研究所、全国農業改良普及支援協会)。
全国から200名余が参加した。
開催挨拶で同研究所の松本所長は「水田を有効活用した飼料生産体制を強化し、飼料イネ、飼料米等を国産飼料として位置づけ、国産飼料に立脚した畜産物生産の研究・普及を課題としている」などと述べた。平成23年度に稲WCSは2万3086ha、飼料用米は同3万3955haと急速に伸びている(トウモロコシは9万2200ha)。基調講演では「水田の飼料作利用と畜産の発展戦略」と題し、名古屋大学大学院の淡路和則教授が次のように話した。
1:飼料米推進の意味は、現有の経営資源(技術も含む)の活用で、水田を水田として利用できる。かつ稲は収量が安定している作物である。米は、作付け面積2位の飼料作物になった。また、飼料米の副産物である稲ワラの広域利用も進めるべきだ。
2:養豚農場の基礎調査(平成21年度)によると、エコフィード利用農場は、飼料米利用に積極的で、そのポイントは農場における自家配合施設の有無にある。
3:一部のアンケート調査ではあるが、飼料用米給与畜産物(豚肉・卵)は通常価格よりも約10%高でも購入意思が強い。
4:所得の違いによる購入価格の違いは1から2割、むしろ年齢が高くなると量より質に変化していく傾向があるので、今後の人口構成を考え、マーケットの対象を考えながら、飼料米を利用していく必要があるだろう。
行政の取り組みとして、農水省畜産振興課の小宮班長は、「飼料用稲の生産・利用を推進する施策の展開」を解説。飼料用米の生産目標を平成32年に70万haとし、そのため、飼料イネWCSは生産者と需要者間での供給計画の策定や、さらなる品質の向上などが課題とし、飼料用米では生産コストの低減、反収の向上、産地と畜産農家とのマッチング、消費者との連携(耕畜消連携)、流通・保管コストの縮減などが克服すべき点とし、稲WCS・飼料用米の生産・利用の拡大に対し、今後もできる限りの施策を行なうと話した。
技術紹介では広島県畜産技術センター・河野幸雄氏が「高糖分飼料イネ「たちすずか」の飼料特性と乳牛への給与」を報告。たちすずかは不消化モミ量が極めて少なく、乾物中の糖分が高く、良好なサイレージ調製に有利で、乳牛の給与でも高い消化性をもつ画期的な品種であるとし、多様な家畜への利用を実現できるとした。
畜産草地研究所の野中和久氏は、飼料用米の加工(ソフトグレインサイレージ、圧ペン籾米・玄米、粉砕籾米・玄米)をしてもCP、EE、デンプン含量等は変化しないが、蒸気圧ペン処理により繊維含量は低下する、などとしたうえで、牛では籾米を物理的処理しないと第一胃内では分解されにくいと報告した。また各県の研究機関の結果を紹介し、これまでの成績では乳牛(泌乳中期から後期)への給与はソフトグレインサイレージでTDN換算で濃厚飼料の30%代替え可能と示唆した。
「飼料用イネの広域流通のための基準策定と技術開発の今後の展望」では、同研究所の浦川修司氏が、流通基準が策定されたことにより、地域内での顔の見える取引から、広域的な顔の見えない場合でも、安全・安心が担保されるとし、今後は、生産履歴管理システムの構築が必要であり、現在そのシステムを開発中であると報告した。
20日(火)の現場からの事例では、「コントラクターを核とした水田農業に立脚した肉牛生産モデルの構築」(滋賀県畜産技術振興センター・土井真也氏)、「地域型コントラクターを核とした飼料イネ・飼料ムギ生産への取り組み」(群馬県中部農業事務所普及指導課・石田豊氏)、「岡山県におけるコントラクターの連携によるイネWCS生産体制」(岡山県美作県民局農林水産事業部・串田晴彦氏)が飼料米および稲WCSの現状を報告する。
詳細は弊誌2月号で。(文責:関東支局)