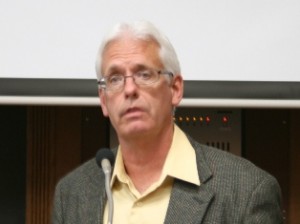ヒートポンプによる生乳のプレクーリングで温水を生成:農研機構の産学官連携セミナー
2012 年 9 月 26 日
独立行政法人農業・食品産業技術研究機構(農研機構)は25日、2012年度第3回産学官連携交流セミナーを開いた。今回のテーマは「農作物や牛乳の生産・調製における省エネルギー対策」で、同機構の3つの研究所が4つの成果を発表し、参加者らと意見交換を行なった。
酪農分野では、畜産草地研究所畜産環境研究領域の石田三佳主任研究員が、CO2ヒートポンプによる生乳のプレクーリングシステムにより熱交換で温水ができるシステムの導入事例を報告した。
これは、CO2ヒートポンプとアイスビルダおよび貯温水タンクを、従来の冷却システムに付設するもの。実証試験は2つの酪農場で行われた。その結果、エネルギー消費量、ランニングコスト、CO2排出ともに削減し、化石燃料の使用量が削減可能と示唆された。生成された温水(80℃)はミルカーやバルクの洗浄、家庭内利用、牛の飲水などに利用できる。
*関連記事 DairyJapan 2011年1月号
「生乳冷却・洗浄用温水生成のランニングコストを削減しCO2も削減する」
*問合せ 農研機構 連携広報センター
http://www.naro.affrc.go.jp
TrackBack URL :
Comments (0)