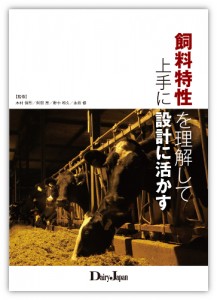原料乳・エネルギー価格上昇で減収減益:森永乳業(株)
2014 年 11 月 12 日
森永乳業(株)は11月11日、都内で平成27年3月期第2四半期の決算を発表した。発表による、同期の売上高は、3158億円(前期比98.4%)、営業利益52億円(前期比53.5%)で、減収減益だった。主な減益要因として、原料・エネルギー価格の上昇、原料乳価格の上昇があげられる。また、夏場の天候不順により売上数量が減少したことも減益要因の一つとしてあげられる。
売り上げ状況については、市乳部門において、「あじわい便り」「マウントレーニアカフェラッテ」シリーズ、「濃密ギリシャヨーグルトパルテノ」などは前年を上回ったが、「森永のおいしい牛乳」リプトンミルクティー」「ビヒダスヨーグルト」等が前年を下回ったことから、市乳の売上高は1075億円(前年比98.6%)となった。
なお、27年3月期第2四半期の集乳量は全国で38万4000t(前期比95.5%)、北海道23万1000t(前期比94.7%)、都府県15万3000t(前期比96.8%)であった。
TrackBack URL :
Comments (0)