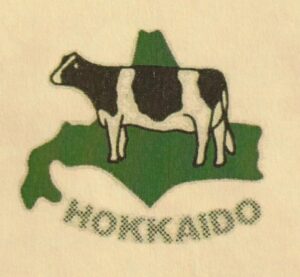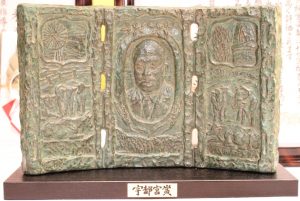第48回 優良登録委員表彰 北海道ホル農協・ホル協北海道支局
2023 年 3 月 4 日
北海道ホルスタイン農協および日本ホルスタイン登録協会北海道支局は3月1日、令和4年度の優良登録委員を発表した。
同農協および同協会支局は、北海道内で長年にわたり登録業務に精励し、地域の酪農振興、乳牛改良・登録事業の普及推進と指導に貢献している登録委員および担当者を毎年表彰している。
今年度の表彰者は以下の14名(敬称略)。
なお表彰式の開催は昨年に引き続き中止となった。
石狩地区:川井良一(北海道農業共済組合)
空知地区:脇渕洋司(北海道農業共済組合)
上川地区:田口英司(有限会社 士別動物病院)
道南地区:葛井史紘(今金町農業協同組合)
胆振地区:小林信輝(とうや湖農業協同組合)
十勝地区:中島祐三子(芽室町農業協同組合)
釧路地区:松田貴久(北海道農業共済組合)
釧路地区:行田祐市(釧路丹頂農業協同組合)
根室地区:前田伸介(道東あさひ農業協同組合)
根室地区:金森直也(道東あさひ農業協同組合)
網走地区:藤原直樹(小清水町農業協同組合)
網走地区:村田明裕(北海道農業共済組合)
宗谷地区:宮原勇太(北宗谷農業協同組合)
留萌地区:仁木孝(るもい農業協同組合)
TrackBack URL :
Comments (0)