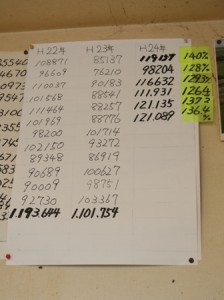「見える化」のすすめ
2012 年 10 月 5 日
生産量を伸ばすことを第一の目標としている十勝管内のTさん。
毎月の出荷乳量(数字)を牛舎の事務所の壁に貼り、
対前年比もはっきりと明示しています。
いわゆる「見える化」です。
Tさんは、こうした「見える化」でモチベーションを上げ、
出荷乳量を増やしていくための戦略を練り、
さらにボトルネック(進行の妨げとなる点)を改善するための努力、
情報収集に余念がありません。
「見える化」は確かに効果あります。
TrackBack URL :
Comments (0)