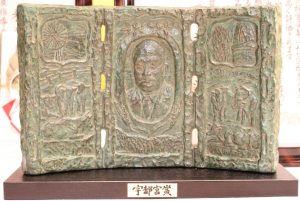酪農学園大学エクステンションセンターは1月27日、同大学で、酪農学園ミルク産業活性化推進事業シンポジウム「牛乳の良さを見直そう~牛乳の生産から活用まで~」を開催した。
一般市民、管理栄養士、中高生、大学生などが参加した。
牛乳に関する研究を行なっている3氏が、牛乳に対する理解を深めてもらおうと、わかりやすく講演した。
まず、中辻浩喜氏(酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類 教授)が「ウシってすごい! 草から牛乳を作り出す仕組みとその意義」と題して、草から牛乳を作り出す仕組み、酪農生産における土・草・牛を巡る物質循環の重要性などを講演した。
次に、栃原孝志氏(酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 講師)が「朝の食卓だけではもったいない牛乳」と題して、牛乳の消費動向、牛乳を飲む必要性、ペットボトルでの牛乳販売が認められるようになったことでの新たな牛乳飲用シーンへの期待などを講演した。
最後に、寺田新氏(東京大学 大学院総合文化研究科 准教授)が「運動と組み合わせた牛乳の効果~最近の話題~」と題して、スポーツ栄養学から見た牛乳を解説した。以下はその概要。
アスリートの身体はトレーニングだけで出来上がったものではなく、何を食べたのか、ということが重要な要素となっている。運動後に蛋白質を補給することで、筋肉の分解を抑制し、合成を増やすことができる(筋肉が太くなる)。牛肉も牛乳も、トレーニング後の筋肉の蛋白質合成効果はほぼ同じ。ということは、運動後に必要な蛋白質補給は、肉やサプリメントに比べて牛乳のほうがリーズナブル(価格が手頃で合理的)であると言える。
乳脂肪分も筋肉の蛋白質を増やすのに重要と思われる。
牛乳にはスポーツドリンクとほぼ同様の電解質の量が含まれているので、運動後や熱中症予防の水分補給としても有効である。
トレーニング量の向上や好結果のためには、運動後なるべく早く糖質を補給することも重要である。その際、牛乳も一緒に摂るとグリコーゲンの回復が良くなる(“粉末コーヒーミルクの素”は合理的)。
このように運動後の牛乳摂取は効果的である。
※詳報はDairy Japan 3月号で