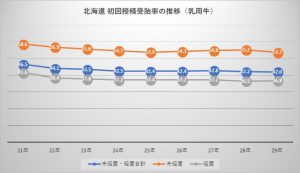バイオガスプラントと圃場管理システムの現状を研修 北海道TMRセンター連絡協議会
2018 年 8 月 3 日
北海道TMRセンター連絡協議会は8月3日、札幌市で「第11回 夏期研修会」を開催した。道内TMRセンター会員はじめ関係者ら約270人が参加した。
佐々木二郎会長(浜頓別エバーグリーン)は開会挨拶で、「今年の北海道は天候不良で、いまだに一番牧草の収穫が終わっていない圃場があるうえに、二番牧草の収穫を開始しなければならない圃場もある状況。今秋から来年1年間は、粗飼料の栄養不足と品質不良が甚大な影響を及ぼすことが懸念される」と現状報告した。
今年の研修は、バイオガスプラント、PCやスマホを使った圃場管理システムに焦点を当て、二つのテーマが企画された。
テーマ1「TMRセンターにおける再生エネルギーの活用」では、竹内良曜氏(北海道バイオマスリサーチ)、横浜隆則氏(コーンズ・エージー)、土谷雅明氏(土谷特殊農機具製作所)の3氏が、バイオガスプラント導入の効果や消化液の効果、各社の取り組み・実績などを発表した。
テーマ2「TMRセンターにおける圃場管理システム」では、藤原拓真氏(ウォーターセル)、安房見悟氏(北海道クボタ)、関口健二氏(十勝農業試験場)、大野宏氏(レポサク)の4氏が、PC・スマートフォンを活用した圃場管理システム(アグリノート、KSAS、レポサク)の内容、ICTの進歩と作業管理手法などを紹介した。
さらに情勢報告として、児玉史章氏(農水省北海道農政事務所)が「飼料をめぐる情勢」を報告した。
TrackBack URL :
Comments (0)